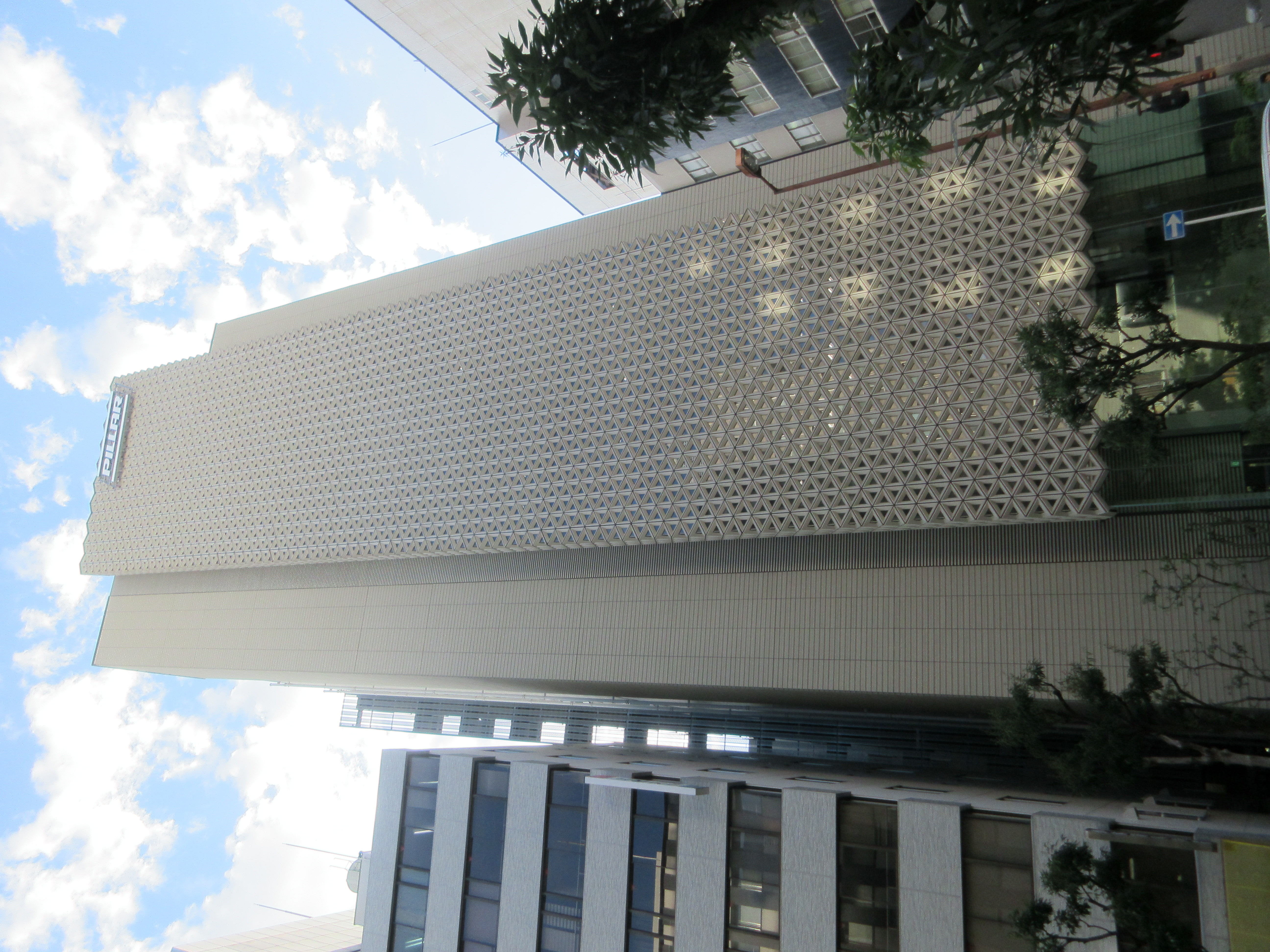TCFD提言に基づく情報開示
頻発・激甚化する風水害やエネルギー市場の不安定化など、気候変動が地球環境や市民生活に及ぼす影響の範囲・程度が拡大しています。気候変動の緩和・適応のために企業が果たすべき役割の重要性はますます高まっており、当社グループにおいても気候変動を重要な社会的課題として捉えております。
また、当社グループのお客様や市場においても、脱炭素・カーボンニュートラルの取り組みが急速に進んでいます。新しいクリーンエネルギーへの転換やエネルギー利用の高効率化に欠かせない半導体の需要の高まりが予想されており、当社グループの技術・製品を通じた市場・社会の脱炭素化への貢献度をさらに高めていきたいと考えています。
このような認識・考えのもと、気候変動に関わるリスク・機会が当社グループの事業・戦略・財務に与える影響について、ステークホルダーの皆様と対話を深めていくことが重要であると考え、TCFD提言に基づく当社グループの体制・取り組み等について開示いたします。
ガバナンス
■気候変動課題の位置づけ
当社グループでは気候変動を最も重要な社会課題の一つとして認識し、2022年にTCFDを支持する署名を行いました。
気候変動の緩和・適応のために企業が果たすべき役割の重要性がますます高まる中、「脱炭素と省エネルギー」を一番初めのマテリアリティとして設定しております。
気候変動の緩和と適応に向けては、2021年度の取締役会の決議を経て、TCFD提言に基づく情報開示を実施し、以下の中長期目標を設定しております。
- • グループ全体のScope1+2において、
- ⁃ 2030年度のCO2排出量を2023年度比で50%以上削減
- ⁃ 2050年度のCO2排出量を実質ゼロ
- • 2030年度における脱炭素社会実現に貢献する製品の売上高を約60億円とする。
■ガバナンス体制
当社グループでは気候変動を含む各種サステナビリティに関連する委員会の上位組織として「ESG/SDGs推進委員会」を設置しており、気候変動に関しては、下部組織である「脱炭素・地球環境委員会」で策定された基本方針や目標設定の審議、目標達成に向けた進捗状況のモニタリングなどを行っております。
取締役会の監督責任
取締役会は、気候変動を重要な経営課題と位置づけ、以下の監督責任を担っています。
- • 気候変動戦略と目標の最終承認
- • 気候関連リスクと機会の監視・監督
- • 気候変動対応の進捗状況の定期的レビュー(半期ごと)
- • 気候変動関連の投資判断の承認
ESG/SDGs推進委員会
「ESG/SDGs推進委員会」では代表取締役社長が委員長を務めており、気候変動関連においても、代表取締役社長が最高責任と権限を有しております。委員会メンバーは、サステナビリティに関連する委員会の委員長と主要コーポレート部門の責任者で構成され、全社的な視点での気候変動対応を可能にしています。委員会は原則として四半期ごとに開催され、審議内容は定期的に取締役会に報告されます。
同委員会は気候変動に関する以下の役割を担っています。
- • 気候変動を含むサステナビリティ戦略の策定と推進
- • 気候関連リスクと機会の管理状況のモニタリング
- • 気候変動目標の設定と進捗モニタリング
- • 気候変動対応に関する全社的な意思決定 等
脱炭素・地球環境委員会
「脱炭素・地球環境委員会」は、常務執行役員を委員長とし、各事業部門で構成されています。同委員会は以下の責務を負っています。
- • 気候変動に関する目標設定
- • 気候関連データの収集・分析・評価
- • 各事業部門における気候変動対応の推進と調整
- • 気候変動リスクと機会の特定と対応策の検討
同委員会は四半期ごとに開催され、その活動内容と進捗状況は「ESG/SDGs推進委員会」に報告されます。
リスク管理
■リスク管理体制
当社グループの気候関連リスク管理は、「脱炭素・地球環境委員会」を中心に実施しています。同委員会は、気候変動に関連するリスクと機会の特定、評価、モニタリングを担当し、四半期ごとに「ESG/SDGs推進委員会」に報告を行っています。
リスク管理の全体統括は「リスクマネジメント委員会」が行い、気候関連リスクを含む全社的なリスク管理の仕組みを構築・運用しています。両委員会は密接に連携し、気候変動対応の実効性向上を図っています。
リスクマネジメント委員会
「リスクマネジメント委員会」は、取締役副社長執行役員を委員長とし、各事業部門長で構成されています。同委員会はリスクマネジメントの強化を推進するため、以下の責務を負っています。
- • 定期的な重要リスクの抽出・分析・評価及びリスク対策の策定
- • 定期的なリスク対策の見直し、是正処置の検討
- • 重要リスクの顕在化に伴う対策、再発防止策などの検討
- • 取締役会への報告
同委員会は年4回開催され、気候関連のリスク管理と進捗状況を含めて「ESG/SDGs推進委員会」に報告されます。
■リスク・機会の識別・評価・管理プロセス
リスク・機会の識別・評価プロセス
当社グループでは、「脱炭素・地球環境委員会」の主導の下、重要な気候関連リスク・機会の見直し・特定までの一連のプロセスを最低年1回実施しています。
このプロセスでは、まず、国際的な気候変動政策や規制動向、業界動向、技術革新、気候・気象の状況などの社内外の最新情報を基に、グループ全体およびバリューチェーン全体でのリスク・機会を識別します。
識別されたリスク・機会は、「影響度」、「発現・実現の時期」、「発現・実現の可能性」の3つの観点から評価・整理します。これらの評価結果を総合的に勘案し、当社グループの事業戦略や財務計画に重大な影響を与えるものを重要なリスク・機会として特定しています。
リスク・機会のモニタリング
特定された重要な気候関連リスク・機会は、適時、「脱炭素・地球環境委員会」において、CO2排出量、環境貢献型製品・サービスの売上高、気候変動対応投資の進捗状況などのKPIを基にモニタリングしています。モニタリング結果は、四半期ごとに「ESG/SDGs推進委員会」に報告され、必要に応じて対応策の見直しを行っています。
全社的リスク管理プロセスとの統合
「リスクマネジメント委員会」と「脱炭素・地球環境委員会」が連携・協議の上、特定された重要な気候関連リスク・機会は全社リスク管理プロセスに統合されます。気候関連の重要リスクは全社リスクマップに組み込まれ、リスク対応策は中期経営計画や年度事業計画に反映されます。「ESG/SDGs推進委員会」への定期報告を通じて、全社的なサステナビリティ戦略との整合性を確保しています。

戦略
当社グループでは、上記の「リスク管理」の仕組み・プロセスの下、特定した重要な気候関連リスク・機会について、その分析と対応を強化し、関連情報の開示拡充を進めています。
■将来の世界観
当社グループの事業・戦略・財務に影響を及ぼす気候関連リスク・機会の識別にあたり、①脱炭素化が進展する1.5~2℃の世界観、②成り行きで温暖化が進行する3~4℃の世界観を整理し、それぞれのシナリオにおいて、当社グループへの影響度が大きいと想定される気候関連ドライバーを抽出・整理しました。
【将来の世界観と主な気候関連ドライバー】
| 将来の世界観 | ① 1.5~2℃シナリオ(脱炭素社会) | ② 3~4℃シナリオ(成り行きの社会) | |
|---|---|---|---|
| 脱炭素社会への移行に伴う社会変化が事業に影響を及ぼすシナリオ | 気候変動緩和策が奏功せず、成り行きで温暖化が進行した状況が事業に影響を及ぼすシナリオ | ||
| 今世紀末までの平均気温の上昇を1.5~2℃に抑え、持続可能な発展を実現させるために、野心的な政策や環境技術革新が進められる。 | パリ協定に則して各国が目標達成に向けた政策を実施するも、各国の協調、環境技術開発、エネルギー転換等が不十分なものとなり、今世紀末までの平均気温が3~4℃程度上昇する。 | ||
| 主な気候関連ドライバー | 政策・規制 | •グローバルでのカーボンプライシングとカーボンプライス上昇 | •カーボンプライスは低価格で推移 |
| 市場 | •自動運転の普及 •通信・情報処理技術の進展による半導体需要の増加 |
||
| •エネルギー源の化石燃料からクリーンエネルギーへの転換 •電源構成の「再エネ+原子力」へのシフト •EVシフトの進展 •炭素集約度の高い原材料(鋼材等)の価格高騰 |
•化石燃料依存の継続、化石燃料価格の高騰 •火力発電所の稼働継続 •内燃機関搭載車の販売継続 |
||
| 技術 | •脱炭素社会に向けた技術開発競争の激化 •CCUS※1技術開発の進展、CO2移送量の増加 |
─ | |
| 気象・気候、環境の変化 | ─ | •水害の頻発化・激甚化 •水資源の枯渇や水質悪化 |
|
| 主な参照シナリオ | IEA※2NZE(2050年ネットゼロ排出シナリオ) IEA APS(表明公約シナリオ) IPCC※3RCP(代表濃度経路シナリオ)2.6 |
IEA STEPS(公表政策シナリオ) IPCC RCP(代表濃度経路シナリオ)8.5 |
|
※1 CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage(二酸化炭素回収・有効利用・貯留)
※2 IEA:International Energy Agency(国際エネルギー機関)
※3 IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)
■重要なリスク・機会の特定
当社グループでは、重要なリスク・機会として以下のように特定しています。
時間軸については、短期(3年以内)、中期(3年超10年以内)、長期(10年超)と定義しています。
【リスク】
| リスクの内容 | 時間軸 | リスク対策 | |
|---|---|---|---|
| 政策・規制 | 自社のGHG排出量に応じたカーボンプライスの負担 | 中期 | 省エネ・創エネの取り組み推進によるGHG排出量の削減 |
| 市場 | 脱化石燃料による、電力・エネルギー市場における流体制御機器の需要減 | 中期~長期 | エネルギーシフトやEVシフトの動向の注視と戦略的な対応 |
| 内燃機関搭載車向け流体制御機器の需要減 | 短期~中期 | ||
| 技術 | 脱炭素社会に向けた技術・製品の開発競争の激化 | 中期 | 省エネ、省資源、省スペースなど、環境負荷低減を考慮した技術・製品の研究開発の加速 |
| 気象・気候、環境の変化 | 自社の主要拠点、及びその周辺における水害の発生 | 短期 | 高リスクの拠点における防災対策の推進、拠点間の連携体制の強化、及びBCPの見直し・強化 |
【機会】
| 機会の内容 | 時間軸 | 機会獲得施策 | |
|---|---|---|---|
| 市場 | 社会経済活動の効率化に向けたデジタルトランスフォーメーション(DX)等の進展に伴う半導体関連製品の需要増 | 短期 | 情報・通信・制御市場における技術革新や市場動向の注視と、タイムリーな新製品投入 |
| 水素、アンモニア、バイオマス燃料など、クリーンエネルギー市場における流体制御機器の需要増 | 中期~長期 | クリーンエネルギーの流体を扱う市場におけるニーズ把握と市場開拓の推進 | |
| 太陽光発電の増加、分散型電源の普及による半導体関連製品の需要増 | 短期 | 再エネ市場の拡大、分散型エネルギー社会への移行を踏まえた電力市場向けの半導体・液晶関連製品の安定的供給 | |
| EV、自動運転車向け車載半導体・デバイスの増加に伴う半導体関連製品の需要増 | 短期 | モビリティシフトに伴うニーズ把握と市場開拓の推進 | |
| 技術 | CO2の輸送・移送、流体制御に資する流体制御機器の需要増 | 中期 | CCUSの商用段階に至るまでの研究開発の加速、実証試験等への参画 |
| 気象・気候、環境の変化 | 排水設備・ポンプ関連製品の需要増 | 短期 | 社会課題解決型の事業展開 |
| 海水淡水化・浄水化関連製品の需要増 | 長期 |
■以下のシナリオにおいて顕著となることが想定されるリスク・機会
- 1.5~2℃シナリオ
- 3~4℃シナリオ
■時間軸(発現・実現の時期)
短期:3年以内、中期:3年超10年以内、
長期:10年超
■シナリオ分析の実施
特定した気候関連リスク・機会の中から、今後の事業への影響(財務影響等)、事業戦略との関連性を考慮し、
テーマ1:自動車市場向け製品におけるEVシフトの影響
テーマ2:石油精製市場・ケミカル市場向け製品におけるクリーンエネルギーシフトの影響
についてシナリオ分析を実施しました。
■シナリオ分析を踏まえた事業戦略
シナリオ分析の結果、EVシフトやクリーンエネルギーシフトが当社グループ製品に与える影響は大きいことが認識できました。しかし、気候変動への対応を積極的に進めることで、これらの影響は低減させられ、新たな市場への販売機会の創出・拡大につなげられることも分かりました。
今後、新製品の開発や既存製品の性能向上を進め、取引先との関係も強化することにより、気候変動に対するレジリエンスを高めていきます。具体的には以下の取り組みを推進します。
- • 環境貢献型製品の開発・拡販の加速
- • クリーンエネルギー市場向け製品の技術開発と市場開拓
- • 自社の事業活動におけるCO2排出量削減の推進
- • サプライチェーン全体でのGHG排出量削減の取り組み強化
- • 気候変動による物理的リスクへの対応強化(BCP見直し等)
これらの戦略を通じて、気候変動がもたらすリスクに適切に対応するとともに、新たな事業機会を創出し、持続可能な成長を実現していきます。
指標と目標
■温室効果ガスの排出量の削減目標
当社グループでは、気候変動の緩和に向けて、省エネルギー活動や自社サイト内での太陽光による自家発電など、温室効果ガスの排出量の削減に積極的に取り組んでいます。
2025年度に目標の見直しを実施し、より実効性の高い削減計画を策定しました。この見直しでは、基準年を2013年度から2023年度に変更し、科学的根拠に基づく削減経路(SBT)の考え方を取り入れています。今後も脱炭素社会の実現に貢献するために、パリ協定や日本政府の方針等を踏まえ、以下の目標で取り組みを推進します。
| 基準年 | 2023年度(14,861 t-CO2) |
|---|---|
| 短期目標: | 2025年度のCO2排出量を2023年度比「25%以上削減」 |
| 中期目標: | 2030年度のCO2排出量を2023年度比「50%以上削減」 |
| 長期目標: | 2050年度のCO2排出量「実質ゼロ」 |
上記目標の達成に向けて、更なる省エネ活動の推進、再生可能エネルギーの導入拡大、生産プロセスの効率化、およびカーボンオフセットの活用など、複合的なアプローチで取り組んでまいります。進捗状況は定期的に評価し、必要に応じて追加施策を実施します。
第三者検証の取得
当社グループはサステナビリティ開示情報の信頼性向上のため、環境に関するパフォーマンス指標の一部において第三者検証を取得しております。
2023年4月1日から2024年3月31日までを対象とした報告書(環境情報検証報告書)は、「サステナビリティ・データ集2024」をご覧ください。
■経営幹部のインセンティブ
気候関連目標と報酬の連動
当社グループでは、気候変動対応を含むサステナビリティ課題への取り組みを加速させるため、2021年度より代表取締役社長を含む取締役(社外取締役および監査等委員である役員除く)の報酬体系にESG関連指標を組み込んでいます。これにより、短期的な財務業績だけでなく、中長期的な企業価値向上に資する気候変動対策の推進を経営陣に動機付けています。
取締役(社外取締役および監査等委員である役員除く)の業績連動報酬はESG指標の達成度に連動させており、その評価項目の一つとして気候変動への取り組みを重視しています。具体的にはCDP気候変動質問書への回答とそのスコアを重要指標としています。
2023年度は
・気候変動:Bスコア
・水セキュリティ:Bスコア
を得ましたので、評価として110%を適用しました。